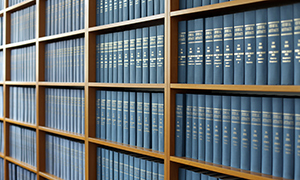2013/11/19
法務情報
【法務情報】生前に父が所有管理していたお墓は誰のもの?
うちには先祖代々のお墓があり,これまでは父が所有管理してきました。ところが,その父が今年亡くなりました。このお墓は誰のものになるのでしょうか。
母は数年前に他界していて,子どもは,数年前に家出をした兄(長男),東京に住む弟(二男),夫と結婚して,父と一緒に暮らしてきた私(長女)がいます。
二男は長男に代わって自分が承継したいと言い,私は,東京にいる弟(二男)より私が承継した方がよいと思っています。
1 遺産分割の問題?
この事例を見ると,少し法律を勉強したことがある方なら「お父さんの財産だから遺産分割をしなければならない。相続人は,子どもたち3人なので,子どもたち3人とで,遺産分割の話合いをして決めることになる・・・」と思うかもしれません。
ところが,法律上は,これは誤りです。民法では,お墓は,相続の対象ではなく,遺産分割の対象にはならないからです。
2 民法上の祭祀に関する定め
民法には,こんな定めがあります。
(祭祀に関する権利の承継)
第八百九十七条 系譜,祭具及び墳墓の所有権は,前条の規定にかかわらず,慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし,被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは,その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは,同項の権利を承継すべき者は,家庭裁判所が定める。
「系譜」というのは,いわゆる家系図や過去帳などです。「祭具」というのは,仏壇や仏具などで,位牌も含むと解釈されています。「墳墓」とは,まさしく墳墓(お墓そのもの)と,その敷地の墓地も含むと解釈されています。
こういった祭祀財産については,土地建物や現預金,保険や株式などと違った取扱いで,以下のとおりの順番で承継されるものと定められています。
① 被相続人(亡くなった方のこと)が指定している場合には,指定された人(1項ただし書)
② 指定した人がいない場合には,慣習に従う(1項本文)
③ 慣習が明らかでないときは,家庭裁判所が定める(2項)
という順番で決めることになっています。
3 遺言→慣習→家庭裁判所
①の“亡くなった人が指定する”というのは,要するに,遺言で指定するということです。亡くなった方が遺言などで,祭祀に関する権利を承継する人を決めていると,その人が承継することになります。
たとえば,最初に書いた事例の中でも,お父さんが亡くなる前に遺言を書いていて,遺言の中で「祭祀は二男に承継させる」と記載していれば,二男が承継することになります。
やはり遺言の威力は絶大です。これから遺言を書く際には,この祭祀の承継者を遺言の中で指定できるということは知っていて損はありません。
次に,亡くなった方が遺言を残していない場合には,「②慣習」で決めることになります。
・・・といっても,この「慣習」というのは,なんともはっきりしないものですので,あまり基準になりません。
慣習も不明な場合には,最終的には③「家庭裁判所が決める」ことになります。では,裁判所はどのようにして決めるのでしょうか。
4 参考となる裁判例
一つの裁判例(東京高判平成18年4月19日)によると,以下のように述べられています。
「承継候補者と被相続人との間の身分関係や事実上の生活関係,承継候補者と祭具等の場所的関係,祭具等の取得の目的や管理の経緯,承継候補者の祭祀主宰の意思や能力,その他一切の事情を総合的に考慮して判断すべき」・・・
つまりは,いままで亡くなった方とどのように暮らしてきたのか(生活関係),お墓と場所的に近いのかどうか(場所的関係),これまでどう管理してきたのか(管理の経緯),その他の家族の意見はどうか(その他一切の事情)などを考慮して決めるということです。
さらにこの裁判例は続けて
「祖先の祭祀は今日はもはや義務ではなく,死者に対する慕情,愛情,感謝の気持ちと言った心情により行われるものであるから,・・・(中略)・・・被相続人からみれば,同人が生存していたのであれば,おそらく指定したであろう者を承継者と定めるのが相当である」
として,被相続人の意思を推定して決めるとしています。
要するに,事例でいうなら,亡くなったお父さんが,仮に生存している場合を想像して,お父さんならおそらくこの人に指定したという人を,裁判所が承継者として定めるのがよい,といっているのです。
亡くなっているお父さんが,生きていたら,誰にお墓を守って貰いたいと考えたか,それを裁判所が決めていくことになります。
◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 大橋 良二◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2013年8月12号(vol.132)>
カテゴリー
月間アーカイブ
- 2025年3月(1)
- 2025年2月(2)
- 2025年1月(2)
- 2024年12月(2)
- 2024年11月(2)
- 2024年10月(1)
- 2024年9月(1)
- 2024年8月(1)
- 2024年7月(2)
- 2024年6月(2)
- 2024年5月(2)
- 2024年4月(1)
- 2024年3月(2)
- 2024年2月(2)
- 2024年1月(1)
- 2023年12月(1)
- 2023年10月(2)
- 2023年9月(2)
- 2023年8月(2)
- 2023年7月(2)
- 2023年5月(1)
- 2023年4月(2)
- 2023年3月(2)
- 2023年2月(2)
- 2023年1月(2)
- 2022年12月(3)
- 2022年11月(2)
- 2022年10月(1)
- 2022年9月(1)
- 2022年8月(2)
- 2022年7月(2)
- 2022年6月(1)
- 2022年5月(1)
- 2022年4月(1)
- 2022年3月(2)
- 2022年2月(1)
- 2022年1月(1)
- 2021年12月(1)
- 2021年11月(1)
- 2021年10月(2)
- 2021年9月(2)
- 2021年6月(1)
- 2021年4月(2)
- 2021年3月(1)
- 2021年1月(3)
- 2020年12月(3)
- 2020年11月(10)
- 2020年10月(5)
- 2020年9月(7)
- 2020年8月(4)
- 2020年7月(3)
- 2020年6月(3)
- 2020年5月(11)
- 2020年4月(5)
- 2020年3月(2)
- 2019年12月(1)
- 2019年9月(1)
- 2019年7月(2)
- 2019年6月(3)
- 2019年5月(2)
- 2019年4月(1)
- 2019年3月(3)
- 2019年2月(2)
- 2018年12月(1)
- 2018年10月(2)
- 2018年9月(1)
- 2018年7月(1)
- 2018年6月(1)
- 2018年5月(1)
- 2018年4月(1)
- 2018年3月(1)
- 2017年12月(1)
- 2017年11月(2)
- 2017年5月(1)
- 2017年3月(1)
- 2017年2月(2)
- 2016年12月(5)
- 2016年8月(2)
- 2016年7月(3)
- 2016年5月(1)
- 2016年4月(2)
- 2016年3月(4)
- 2016年2月(3)
- 2016年1月(1)
- 2015年11月(1)
- 2015年9月(1)
- 2015年8月(1)
- 2015年7月(1)
- 2015年6月(1)
- 2015年4月(1)
- 2015年3月(2)
- 2015年1月(3)
- 2014年9月(6)
- 2014年8月(3)
- 2014年6月(3)
- 2014年5月(3)
- 2014年4月(2)
- 2014年2月(2)
- 2014年1月(2)
- 2013年12月(5)
- 2013年11月(1)
- 2013年10月(5)
- 2013年9月(5)
- 2013年8月(2)
- 2013年7月(2)
- 2013年6月(4)
- 2013年5月(2)
- 2013年4月(3)
- 2013年3月(3)
- 2013年2月(2)
- 2013年1月(1)
- 2012年12月(2)
- 2012年11月(2)
- 2012年10月(1)
- 2012年9月(2)
- 2012年8月(2)
- 2012年7月(2)
- 2012年6月(2)
- 2012年5月(1)
- 2012年4月(2)
- 2012年2月(2)
- 2012年1月(3)
- 2011年12月(2)
- 2011年11月(3)
- 2011年10月(3)
- 2011年9月(8)
- 2011年8月(10)
- 2011年7月(8)
- 2011年6月(8)
- 2011年5月(10)
- 2011年4月(9)
- 2011年3月(9)