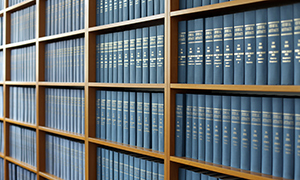2011/06/08
法務情報
【法務情報】「日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。」
表題の一文、何の文章だと思いますか。
「日本国民は何をそんなに誓っているのだろう。」と思われるのではないでしょうか。
実はこれは日本国憲法の制定の動機や理想を書いた「前文」の締め括りの一文です。下に、日本国憲法の「前文」を全文引用します。長くて、読みにくいですが、がんばって読んで、日本国民は何をどのように誓っているか考えてみてください。
日本国憲法には補足を除くと実質的には99の条文しかありません。
しかし、その中に、国民のさまざまな権利、国会のあり方、行政のあり方、裁判所のあり方、地方自治のあり方など国のあり方が規定されています。日本国憲法は日本国民が「このような権利を享受したい。」「このような社会に住みたい。」「このような国にしたい。」といって定めた決まりともいうべきものです。
そして、日本国憲法の諸規定はこの「前文」を動機や理想として作られたといえます。
ところで、民主主義のわが国では国会の多数決によって作られた法律によって政治が行なわれています。法律には罰則が設けられ、これに違反した場合は刑罰が科せられる場合があります。多数派の意見が強制力を持って通用するのです。
しかし、多数決があればどんな法律でも作れるという訳ではありません。公務員である国会議員も憲法を遵守する義務がありますし、憲法に違反する法律は裁判所で違憲の判断がなされ、効力を有しないため、憲法の規定に違反する法律は事実上作ることができません。
その結果、憲法に定められている国民の権利はたとえ国会で満場一致の多数決で定められた法律であっても奪うことはできなくなります。
また、憲法に反する国の制度も法律で設けることができなくなります。
もし、憲法がなかったらどうなるでしょうか。多数決でどんな法律でも作られることになり、その時々の情勢や雰囲気で大きく国のあり方や国民の生活が揺り動くでしょう。多数決に反映されなかった人達の権利は守られなくなってしまいます。多数決での勝者と敗者が交々入れ違ったりするでしょう。
憲法があれば憲法の範囲内で法律が定められるのでこのようなことは避けられます。憲法に定められている国民の権利は奪うことはできません。また、憲法が公平な裁判所の裁判をうける権利や裁判所のあり方を定めていることから、刑事裁判は警察が行うと言うような法律もできませんし、憲法が国会の構成員である国会議員は選挙によって決めるとしていることから、国会議員は世襲で決めるという法律も作ることができません。現在の年金や生活保護の制度を廃止するということに対しても憲法の生存権規定などを根拠に異を唱えることができます。
憲法には、多数決が行き過ぎないように、憲法が定める理念によって一定の枠や方向性を設けるという重要な役割があるのです。
60年以上も前に下に引用する前文を持った憲法が作られ、それに基づいてわが国の諸制度ができあがり、現在の私たちの暮らしがあります。
現在、日本は自信を喪失していると言われていますが、司法試験の受験勉強以来、十数年ぶりに憲法の前文を読み返してみて、自信を取り戻せた気がします。
<日本国憲法前文>
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。」
◆弁護士法人一新総合法律事務所 弁護士 古島 実◆
<初出:顧問先向け情報紙「こもんず通心」2010年7年12月24日号(vol.69&70)>
カテゴリー
月間アーカイブ
- 2025年3月(1)
- 2025年2月(2)
- 2025年1月(2)
- 2024年12月(2)
- 2024年11月(2)
- 2024年10月(1)
- 2024年9月(1)
- 2024年8月(1)
- 2024年7月(2)
- 2024年6月(2)
- 2024年5月(2)
- 2024年4月(1)
- 2024年3月(2)
- 2024年2月(2)
- 2024年1月(1)
- 2023年12月(1)
- 2023年10月(2)
- 2023年9月(2)
- 2023年8月(2)
- 2023年7月(2)
- 2023年5月(1)
- 2023年4月(2)
- 2023年3月(2)
- 2023年2月(2)
- 2023年1月(2)
- 2022年12月(3)
- 2022年11月(2)
- 2022年10月(1)
- 2022年9月(1)
- 2022年8月(2)
- 2022年7月(2)
- 2022年6月(1)
- 2022年5月(1)
- 2022年4月(1)
- 2022年3月(2)
- 2022年2月(1)
- 2022年1月(1)
- 2021年12月(1)
- 2021年11月(1)
- 2021年10月(2)
- 2021年9月(2)
- 2021年6月(1)
- 2021年4月(2)
- 2021年3月(1)
- 2021年1月(3)
- 2020年12月(3)
- 2020年11月(10)
- 2020年10月(5)
- 2020年9月(7)
- 2020年8月(4)
- 2020年7月(3)
- 2020年6月(3)
- 2020年5月(11)
- 2020年4月(5)
- 2020年3月(2)
- 2019年12月(1)
- 2019年9月(1)
- 2019年7月(2)
- 2019年6月(3)
- 2019年5月(2)
- 2019年4月(1)
- 2019年3月(3)
- 2019年2月(2)
- 2018年12月(1)
- 2018年10月(2)
- 2018年9月(1)
- 2018年7月(1)
- 2018年6月(1)
- 2018年5月(1)
- 2018年4月(1)
- 2018年3月(1)
- 2017年12月(1)
- 2017年11月(2)
- 2017年5月(1)
- 2017年3月(1)
- 2017年2月(2)
- 2016年12月(5)
- 2016年8月(2)
- 2016年7月(3)
- 2016年5月(1)
- 2016年4月(2)
- 2016年3月(4)
- 2016年2月(3)
- 2016年1月(1)
- 2015年11月(1)
- 2015年9月(1)
- 2015年8月(1)
- 2015年7月(1)
- 2015年6月(1)
- 2015年4月(1)
- 2015年3月(2)
- 2015年1月(3)
- 2014年9月(6)
- 2014年8月(3)
- 2014年6月(3)
- 2014年5月(3)
- 2014年4月(2)
- 2014年2月(2)
- 2014年1月(2)
- 2013年12月(5)
- 2013年11月(1)
- 2013年10月(5)
- 2013年9月(5)
- 2013年8月(2)
- 2013年7月(2)
- 2013年6月(4)
- 2013年5月(2)
- 2013年4月(3)
- 2013年3月(3)
- 2013年2月(2)
- 2013年1月(1)
- 2012年12月(2)
- 2012年11月(2)
- 2012年10月(1)
- 2012年9月(2)
- 2012年8月(2)
- 2012年7月(2)
- 2012年6月(2)
- 2012年5月(1)
- 2012年4月(2)
- 2012年2月(2)
- 2012年1月(3)
- 2011年12月(2)
- 2011年11月(3)
- 2011年10月(3)
- 2011年9月(8)
- 2011年8月(10)
- 2011年7月(8)
- 2011年6月(8)
- 2011年5月(10)
- 2011年4月(9)
- 2011年3月(9)